見えにくい、読みにくい「困った!」を解決するデザイン
『見えにくい、読みにくい「困った!」を解決するデザイン』を読みました。
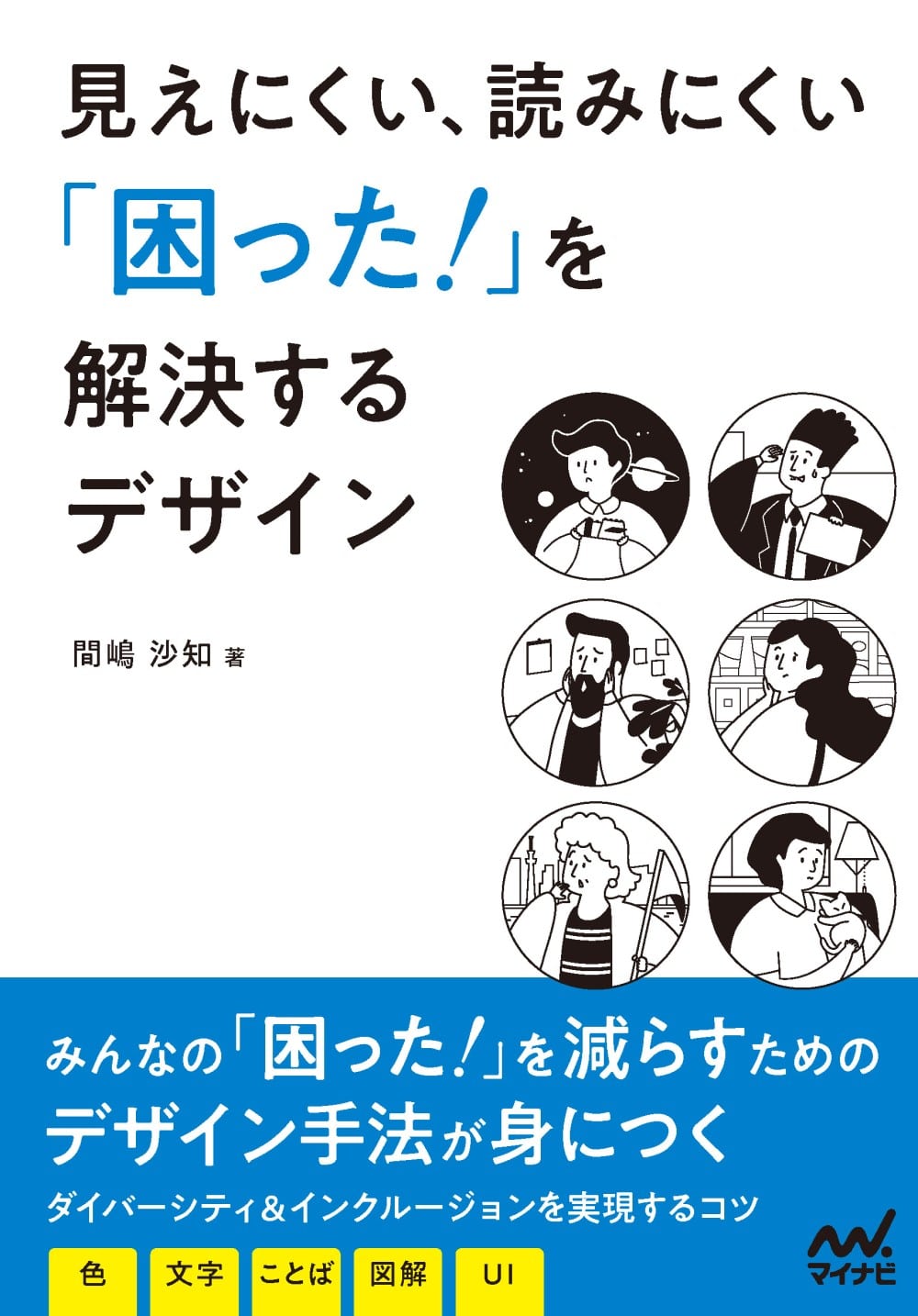
色、文字、ことば、図解、UI のビジュアルデザインについて、アクセシビリティ (あるいはユニバーサルデザイン、インクルーシブデザイン) の観点から「このように改善するとよい」をわかりやすくまとめた書籍です。
本書の大きな特長は、6人の登場人物 (年齢や生活様式、障害の有無など異なるコンテキストを抱える人たち) を立て、その人たちにとっての「困った!」を手がかりに「こうしよう!」というヒントを提示することで、デザイン成果物の向こう側にいるユーザーの多様性を、常に読者に意識づけようとしているところです。UX デザインのマントラに、「偽の合意」効果にうっかり陥らないための戒めとして「You are not the user (あなたはユーザーではない)」がありますが、本書はそれを地でゆく構成になっていると言えるでしょう。この6人の登場人物は、本書の「そで」(表紙のカバーの折り返しの部分) にも書かれており、また、本書の特設サイトでも参照できるようになっているので、読みながらいつでも立ち返りやすくなっています。
内容的には、上述の「色、文字、ことば、図解、UI」のデザインにおける、とりわけ「いかにしたら多様なユーザーに分け隔てなく情報を伝えることができるか」というエッセンスが、平易かつ簡潔にまとめられています。いわゆる「デザイナー」という職能に限らず、「人に何かを伝える」ことに関わるあらゆる人にとって、敷居の低いリファレンスとして重宝するでしょう。アクセシビリティやユーザビリティに興味を持ち始めた初学者にうってつけなのはもちろんのこと、ある程度心得がある人にとっても、いつでも基本に立ち返られるよう手元に置いておきたい良書だと思います。
以下、個人的に興味深く感じた、あるいは改めて学びになったところです。
- 本書の冒頭 (P.11) の「変化したのは人ではなく壁です。壁のデザイン次第で、できることとできないことは変化します。」という記述は、「障害の社会モデル」をわかりやすく端的に言い表わしている。
- 色の役割を「感覚的な役割」と「機能的な役割」の2つに分解して解説し、そのどちらをもバランス良く両立することを説いている。(P.35)
- 色覚特性の原理として、桿体細胞と錐体細胞 (赤、緑、青) のはたらきを踏まえ、その流れで P型、D型、T型、A型の特質をわかりやすく解説している。(P.37〜39)
- 高齢者の色覚特性として、水晶体のはたらきを踏まえ、その流れで白内障の特質をわかりやすく解説している。(P.43〜44)
- ウェブアクセシビリティに携わっていると「色で情報を識別させない」意識になりがちだが (参考 : WCAG 2.1 達成基準 1.3.3 感覚的な特徴)、色には「物事を直感的にわかりやすく、すばやく伝える力がある」(P.35) と説き、色以外の要素 (記号など) での識別性は担保しつつも、色覚特性を持つユーザーに対しても同等に色を介して情報を直感的に伝えるところまで踏み込んでいる。(P.79〜80)
- タイポグラフィの諸側面 (フォント、行間、行長) を検討する際のものさしとして、文字の読みやすさを「視認性 (文字の形のわかりやすさ)」「判読性 (読み間違いの起こりにくさ)」「可読性 (文章の読みやすさ)」という3つの要素に分解している。(P.88)
- 文字の読みにくさを、「文字の形を捉える視覚」「文字に音を結びつけて理解する音韻処理」という2つの要素に分解して解説し (P.91)、その流れでアーレンシンドロームやディスレクシアがどういった障害であるかをわかりやすく解説している。(P.92)
また本書では、大変ありがたいことにコラム (P.32) で、デザイン支援ツール「インクルーシブなペルソナ拡張」をご紹介いただいています。6人の登場人物の視点を通じて多様なユーザーに別け隔てなく情報を伝えるデザインを学んだ皆さんが、実際にご自身のプロジェクトやサービス運用でペルソナを立てた際に、このツールがアクセシブルなプロダクト実現に少しでもお役に立てたとしたならば、とても嬉しいです。